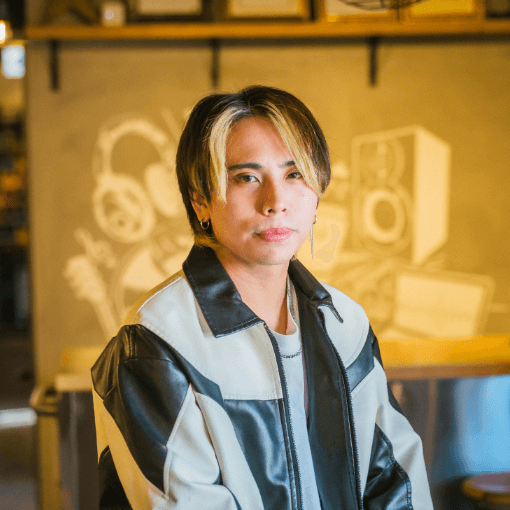【音楽理論】ディグリーネームとは?

みなさん、こんにちは!
今回は音楽理論における、ディグリーネームについて説明していきます!
例えば、Cメジャースケール(ドレミファソラシ)なら、各音は次のようになります:
1度: ド(C)
2度: レ(D)
3度: ミ(E)
4度: ファ(F)
5度: ソ(G)
6度: ラ(A)
7度: シ(B)
このように、1度から7度までの音にはそれぞれ特定の名前と役割があり、コード進行やメロディ作りに役立ちます。
実際にはこの数字はローマ字表記で表せるのがほとんどです。
Ⅰ(1度 )
Ⅱ(2度)
Ⅲ(3度)
Ⅳ(4度)
Ⅴ(5度)
Ⅵ(6度)
Ⅶ (7度)
この表記はキーや例えばマイナースケールになっても主音をⅠとし、そこからⅦまで数えて表記されます。
例えばこんな感じです。


また役割については、次回のブログで説明したいと思います。
例えば、「I – IV – V – I」という進行をCメジャースケールで表すと「C – F – G – C」となります。この進行は他のスケールでも使えるため、Gメジャーで演奏する場合は「G – C – D – G」となります。
例えば「I – V – Ⅵm – IV」という進行は、ポップスでよく使われる進行で、Cメジャーで表すと「C – G – Am – F」になります。この進行は多くの楽曲で使われており、覚えておくと便利です。
このように、ディグリーネームは音楽理論の基礎となる重要な要素で、コード進行やメロディの理解に役立つので必ず覚えてください!
●立川のボイトレスクール「DECO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
今回は音楽理論における、ディグリーネームについて説明していきます!
ディグリーネームとは?
ディグリーネームは、音階(スケール)内の各音に番号をつけ、その音の役割や関係性を示すために使われる名前です。音階内の音にはそれぞれ「第何音」という役割があり、1から7までの数字で表されます。例えば、Cメジャースケール(ドレミファソラシ)なら、各音は次のようになります:
1度: ド(C)
2度: レ(D)
3度: ミ(E)
4度: ファ(F)
5度: ソ(G)
6度: ラ(A)
7度: シ(B)
このように、1度から7度までの音にはそれぞれ特定の名前と役割があり、コード進行やメロディ作りに役立ちます。
実際にはこの数字はローマ字表記で表せるのがほとんどです。
Ⅰ(1度 )
Ⅱ(2度)
Ⅲ(3度)
Ⅳ(4度)
Ⅴ(5度)
Ⅵ(6度)
Ⅶ (7度)
この表記はキーや例えばマイナースケールになっても主音をⅠとし、そこからⅦまで数えて表記されます。
例えばこんな感じです。


また役割については、次回のブログで説明したいと思います。
ディグリーネームの使い方
ディグリーネームを使うと、コード進行やメロディを数字で簡単に表現できるため、他の音階でも同じ進行を使えるようになります。例えば、「I – IV – V – I」という進行をCメジャースケールで表すと「C – F – G – C」となります。この進行は他のスケールでも使えるため、Gメジャーで演奏する場合は「G – C – D – G」となります。
実際にディグリーネームを活用してみよう
実際にコード進行やメロディ作りでディグリーネームを使ってみると理解が深まります。例えば「I – V – Ⅵm – IV」という進行は、ポップスでよく使われる進行で、Cメジャーで表すと「C – G – Am – F」になります。この進行は多くの楽曲で使われており、覚えておくと便利です。
このように、ディグリーネームは音楽理論の基礎となる重要な要素で、コード進行やメロディの理解に役立つので必ず覚えてください!
●立川のボイトレスクール「DECO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!