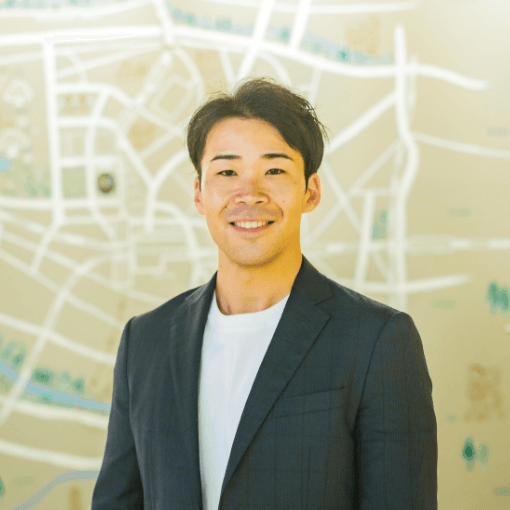低い声の出し方!
.jpeg)
こんにちは! DECO MUSIC SCHOOLの千葉晃樹です!
今回は低い声の出し方、練習方法をご紹介します!
声ってどういう風に出ているの?
.jpeg)
まず声がどのようにして出ているか知ってますか?
声は、肺から送り出された空気が喉の奥にある「声帯」を振動させ、「声帯」がその音の元(喉頭原音)を作り出すことで生まれます。この喉頭原音は、喉、口、鼻などの空間(声道)で共鳴・増幅され、さらに唇や舌の動きによって言葉に形作られ、周囲に伝わります。
声の高さは声帯の緊張度や振動数によって、声の大きさは息の強さ(声門下圧)によって、それぞれ調節されます。
低い声が出るときは、声帯が長く太く、ゆっくりと振動することと、共鳴空間が広くなることで発生します。
声帯の振動数が少なくなると低い音になり、声帯をリラックスさせて喉仏を下げ、息の量を増やすことでより共鳴効果が高まり、魅力的な低音が出やすくなります。
喉と口のストレッチをしよう!
.jpeg)
喉、口、鼻などの空間(声道)を広げるためにはストレッチが必要です。
そのために1番有効的なのが「あくび」です。
人間が1番口を開ける時は「あくび」をしている時です。もっと言うと、あくびをしないと口まわり、喉まわりの筋肉を伸ばすことができません。
やり方はとても簡単です。
①口を開けて、口からたくさん息を吸いましょう。
②息を吸ったら声を出しながら「あくび」をしましょう。
③出している声を低い音から高い音まで出して、できるだけ長く続けるように意識しましょう。
④できる方は「あくび」をしてる時に唇、顔の筋肉を自ら動かしてみましょう。
なんとなく普段からしてる「あくび」。
意識してやろうとしてみると意外と難しく感じる方もいらっしゃいます。
まずは意識して「あくび」をすることを習慣にしてみましょう。
実際に低い声を出そう!
.jpeg)
実際に低い声を出す練習をしないと低い声は出ません。
それでは何を意識して低い声を出したらいいのか?
いくつかポイントをご紹介します!
①小さな声量でゆっくり息を吐く
→低い声はいきなり大きな声で出すことはできません。まずは小さな声量でゆっくり息を吐きながら低い声を出してみましょう。
②「あくび」の口の形で声を出す
→口の中が狭いと、口の中の筋肉が緊張して硬くなり、低い声が出にくくなります。声帯を緩め、リラックスさせて喉仏を下げ、息の量を増やすことでより共鳴効果につながります。
③毎日やろう!
→低いを声を出す習慣を身につけることで、体がその感覚を覚えて声が出るようになってきます。
普段からの意識を変えて、低い声をマスターしましょう!
今回は「低い声の出し方」をご紹介しました。
ボイトレが初めての方でも、基礎から一緒に勉強していきます。
是非これを機会に無料体験レッスンから受けてみてください♪