【低い声を出す方法】|楽に出るコツとトレーニング方法

こんにちは、DECO MUSIC SCHOOLです。
今回はのテーマは「低い声を出す方法」についてです。
「気持ちよく出る音域とのクオリティーに差があって嫌だな…」
「声質をもっとかっこよくしたいな」という方必見です。
練習するにも中々しにくい部分である低音。
体や息の使い方からわかりやすく解説していきます。
低音の仕組み
低い声を出すことに苦手意識を持っている方は意外と多いものです。
高い声が出ないという悩みと並んで、実は相談の多いテーマでもあります。
特に男性の方で「地声が高くて説得力がない」と感じていたり、
女性の方で「落ち着いた低音を出したいけど、喉が苦しくなる」という声も少なくありません。
では、「なぜ低い声が出しにくいのか?」を身体の仕組みから整理し、
無理なく改善するための土台を作っていきましょう。
低音の限界
そもそも低音は練習すればどこまでも出るものなのか?
答えは「no」です。
低音の限界は、声帯の長さで決まります。
もともと持って生まれた声帯の長さ以上の低音は出ません。
なのでポテンシャルを引き出すことが、低音発声の唯一のアプローチになります。
声帯の仕組みと音の高さの関係
声の高さは、主に声帯の「長さ」「厚み」「張り具合」によって決まります。
たとえばギターの弦を思い浮かべてみてください。
短くて細い弦は高い音、長くて太い弦は低い音が鳴りますよね?
声帯もまさにそれと同じです。
なので低い声を出すには、声帯をゆるめて厚みのある状態に保ち、ゆっくりと振動させる必要があります。
しかし、多くの人は日常的に緊張した状態で話したり、歌ったりしています。
声帯が常にピンと張っていると、自然と高音よりの声になってしまうんですね。
よって、まずは「声帯をゆるめる」という感覚を養うことが、低音発声への第一歩です。
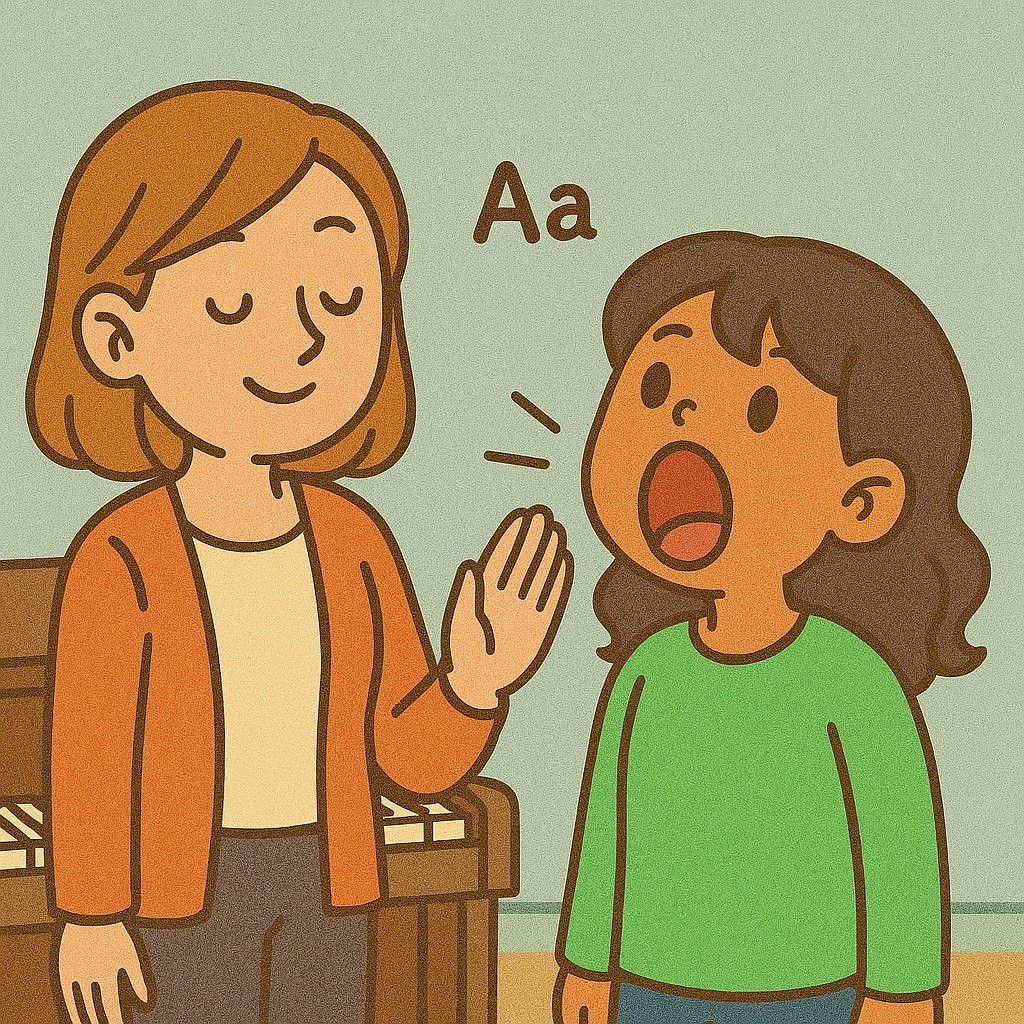
低い声が出せない原因
では、なぜ低音が出しにくくなるのでしょうか?
それは大きく4つの要因に分けられます。
原因①過緊張による声帯の張り
1つ目は「声帯を固めてしまっていること」。
声帯は基本的に力を入れずにコントロールします。
ガチガチに固めて歌ってしまうと、声帯が振るえなくなり、
声の伸びがなくなり、歌いにくさ、しんどさの原因になります。
原因②息を吐きすぎている
2つ目は「息を吐きすぎること」。
声を出そうとするあまり、空気をたくさん押し出そうとする人がいますが、これは逆効果。
低い声を出すには、少量の息で声帯をゆっくり振動させる必要があります。
原因③喉を締めている
3つ目は「喉を締めること」。
喉の力で無理に声を下げようとすると、
かえって声帯が固まり、うまく振動できません。
結果として、苦しそうな声やガラガラ声になってしまうことも。
原因④共鳴ポイントが定まっていない
4つ目は「共鳴ポイントが定まらないこと」。
低音域では、響きを下方向(胸や喉の奥)に誘導することが重要ですが、
その感覚がつかめていないと、ただこもっただけの音になってしまいます。
間違った出し方が喉に与えるリスク
低い声に憧れて、無理やり喉を押し下げるような出し方をしてしまう方も少なくありません。
ですがこの方法、長期的には喉に大きな負担をかけるリスクがあります。
特に注意したいのが、喉の奥にある「喉頭(こうとう)」を力づくで下げようとする癖。
これを続けていると、声帯の炎症やポリープの原因にもなりかねません。
また、喉を無理に使って出した声は、聞いている側にも不自然に響きやすくなります。
いわゆる「作り声」になりやすいのもこのタイプの特徴です。
魅力的な低音を目指すなら、まずは喉に負担のかからない自然なポジションを知ることから始めましょう。
まずは低音を出せるようになりたい方はこちら!
低い声を出すための体づくりと意識
低音発声のポイントは、ただ声を「下げる」のではなく、声を「下支えする」ことにあります。
つまり、出す声そのものよりも、その声が生まれる“身体の状態”を整えることが最優先です。
低い声を無理なく出すために必要な、体の使い方や感覚について理解を深めましょう。
-1024x682.jpeg)
リラックスと脱力
低音を出すには「ゆるめる感覚」がとても大切です。
声帯は筋肉の一種なので、ギュッと力が入っていると、うまく振動できません。
とくに喉や肩、首まわりの緊張は、声の響きを邪魔してしまいます。
試しに、ため息をつくように「はぁ〜」と声を出してみてください。
この時、肩の力が抜けているか、喉が閉まっていないかを確認します。
この「ため息のような声」が、低音発声の基本です。
気持ちもリラックスしていると、自然と声も落ち着いた響きになります。
姿勢を見直す
姿勢が悪いと、息の流れが妨げられ、低音が出にくくなります。
猫背になっていたり、腰が反っていたりすると、腹式呼吸もままなりません。
理想的なのは、背骨が自然なカーブを描き、頭が背骨の上に乗っている、
骨や筋肉が人体模型と同じ配置になっている状態。
軽く前を向いて、肩の力を抜いた“良い姿勢”を作ってみましょう。
口・喉・胸の共鳴ポイントを感じる
低音をしっかり響かせるには、共鳴を「下に誘導する」感覚が必要です。
よく「胸に響かせて」と言いますが、これは単なる比喩ではありません。
ハミングなどの練習を通じて、音の振動がどこに伝わっているかを感じてみてください。
わかりやすいのは、「あー」と普段使ってる地声を出してみて
胸や喉の奥が振動する感覚があれば、そこに音が共鳴している証拠です。
わかりにくい方は実際に胸骨を触りながら発声してみてください。
震えを感じられると思います
これはトンネルに音が響くようなイメージで、
声の響きが広がる場所を体の中に作るということです。
低音域を安定させる練習法
身体の準備が整ったら、いよいよ本格的な練習に入っていきましょう。
低音を安定させるには、声帯のコントロール力と、
響きを意図的に誘導する感覚を養うことが大切です。
ここでは、今日から取り組める3つの練習法をご紹介します。

ハミングで響きを胸に誘導する
声の「響き」をコントロールする感覚を養うには、ハミング練習がとても効果的です。
口を閉じて「ん〜」と声を出すことで、
鼻腔や喉の奥、胸に音の振動が伝わっていくのを感じ取ることができます。
手で振動を感じられると思います。
低音ハミングを行う際は、特に「胸が響いているか」を意識しましょう。
これはいわば、音の共鳴場所をチューニングしているようなもの。
できるだけ下の方に響きが伝わるよう、
リラックスした姿勢と呼吸で試してみてください。
また、空気は冬場に手を温めるときに吐くような、
生暖かい空気を意識して吐いてみてください。
さらに発展として、「ん〜」のまま少しずつ口を開けて「あ〜」に移行していく練習も有効です。
響きをキープしたまま、発音に変えることで、実際の歌唱にもつながっていきます。
呼吸の基本を忠実に
呼吸はもちろん腹式呼吸が基本です。
低音や高音など難しい発声になればなるほど、腹式呼吸が力を発揮します。
逆に言えば、腹式呼吸ができないと音を狙うこと自体が難しくなります。
いつも以上に呼吸に目を向けてあげてください。
下腹部に空気を溜める感覚を持ち、そこから“少量ずつ吐く”イメージで声に変えていきます。
特に低音は、吸うよりも「ゆっくりと、一定量の息を均一に吐く」ことが大切です。
「目の前にあるろうそくの火を揺らさないように息を吐いて」みるとイメージしやすいと思います。
これができると、声がグッと落ち着いた響きになります。
もっと綺麗に低音を出したい方はこちら!
低い声を魅力的に響かせるために
低音が出せるようになっても、それが「聞き手にとって魅力的に響く声」でなければ、なかなか印象には残りません。
ここからは、低い声に芯や表現力を加えるための視点とテクニックを紹介します。
単なる“低さ”ではなく、“深さ”や“説得力”として響く声を目指していきましょう。
声の「芯」と「太さ」の作り方
低い声に必要なのは、「太い声」ではなく「芯のある声」です。
この違いはとても大切で、息の量を増やして無理に太くしようとすると、
逆に響きがぼやけたり、喉に負担がかかったりします。
「芯のある声」とは、少ない息で効率的に振動している声のこと。
これはまさに、エッジボイスやハミングで練習してきた「声帯をしっかり閉じる」感覚と一致します。
たとえばウィスパー気味のささやき声でも芯があると、ちゃんと通る声に聞こえますよね。
この「芯」は、声帯と息のバランスが整ってくると自然と出てきます。
ポイントは“息を押し出す”のではなく、“音を届ける”意識に切り替えること。
声が空気に乗って、遠くに運ばれていくようなイメージで出してみてください。
地声と裏声の境界を見極める
低い声の中にも「裏声っぽく聞こえる」「こもって聞こえる」という悩みがあります。
その原因のひとつが、地声と裏声の境界があいまいなまま、
音域を無理に下げていることです。
この境界をはっきり認識するためには、
自分の「地声で出せる最低音」と「裏声に切り替わるギリギリの音」を知ることが効果的です。
ピアノアプリやチューナーを使って、自分の最低音を毎日チェックしてみましょう。
そうすることで、音程の安定感だけでなく、声の“キャラクター”にもブレがなくなります。
また、地声と裏声を意図的に切り替える練習を繰り返すことで、
それぞれの声区に対する理解が深まり、
結果として“コントロールされた低音”が育っていきます。

低音でも聞き取りやすい発音のコツ
低い声は、音域的にどうしても「こもりやすい」傾向があります。
特に母音が弱くなると、モゴモゴとした印象になってしまい、
説得力が半減してしまうのです。
そこで重要なのが「口の開け方」と「発音の明瞭さ」。
ポイントは、口の中に“縦の空間”をしっかり確保することです。
いわゆる「あくびの口」を意識してみましょう。
「う」と発音するときのように唇を窄めたまま、「あくびの口」をすると、
縦に口を開く感覚がさらにわかりやすくなると思います。
また、唇や舌先の動きをハッキリと意識することで、言葉がよりクリアに響きます。
さらに、息の量を必要以上に増やさず、音の芯を保ったまま発音することも大切です。
これにより、聴き手にとっても聞き取りやすく、自然な低音として伝わります。
よくある質問(Q&A)
Q1. なぜ低い声が出しにくいのですか?
声の高さは声帯の「長さ・厚み・張り具合」で決まります。日常的に声帯が緊張しやすく、ピンと張った状態だと自然に高めの声になります。低音は、声帯をゆるめてゆっくり振動させる感覚がカギです。
Q2. 低い声を出そうとすると喉が苦しくなります。なぜですか?
喉の力で無理に下げようとすると声帯が固まり、振動しにくくなるためです。リラックス姿勢と少ない息量で、喉に力を入れず響かせる方法へ切り替えましょう。
Q3. 低音発声に向いていない人もいますか?
声帯の長さによって低音の“物理的な下限”は個人差があります。ただし呼吸・脱力・共鳴の習得で、誰でも自分の声域内で魅力的な低音を育てられます。
Q4. 喉に負担をかけずに低音を出すコツは?
喉頭を力で押し下げる方法は避けましょう。ため息のような「はぁ〜」で脱力を確認し、腹式呼吸でゆっくり一定に息を吐くのが基本です。
Q5. 低音を響かせる効果的な練習は?
口を閉じたハミング(ん〜)が有効です。胸や喉の奥の振動を手で触れて確認し、そのまま「あ〜」へ移行して響きを保った発音に発展させます。
Q6. 低音がこもって聞こえるのはなぜ?
口腔内の縦空間不足や発音が不明瞭なことが原因です。「あくびの口」で縦に開け、舌先・唇の動きをはっきりさせ、息量を増やしすぎないことで芯を保ちます。
まとめ|低い声は「練習」で必ず育てられる
低音は、生まれつきの才能ではなく、「育てる声」です。
身体の使い方、呼吸のコントロール、響きの誘導、
そして何より“力を抜く感覚”をつかむことで、
誰でも無理なく魅力的な低音を手に入れることができます。
今日ご紹介したトレーニングは、どれも地味でシンプルなものばかりかもしれません。
でも、声は確実に応えてくれます。
焦らず、毎日少しずつ取り組んでみてください。
話だけでも聞いてみたい方はこちら!

