歌が上手くなるトレーニング方法

こんにちは、DECO music school です。
今回は1人でできるトレーニングをお話ししていきます!
実は歌って、想像以上にたくさんの要素があります。
それをひとつひとつ分解して練習して、くっつけて練習して…を何度も何度も繰り返して、ちょっとずつ出来るようになっていくという風にまずは考えていてください。
つまり一言に「歌が上手くなる」と言っても、しなきゃいけないトレーニングはたくさんあると言うことです。
発声の基礎を固める
まず最初に発声の基礎を固めましょう。
安定して声を出せるようになると、それだけでも歌のクオリティーがグッと上がります。
発声の基礎に関しては主に以下の内容です。
- 腹式呼吸
- 共鳴
- 声帯閉鎖
腹式呼吸とは?
人間が行う呼吸の種類は主にふたつあります。
胸式呼吸と腹式呼吸です。胸式呼吸は文字通り胸を使うような呼吸です。
例えば全力で走った後や緊張している時など、「早く酸素がほしい」と思う時には、
胸が持ち上がりお腹が凹む状態で息を吸います。
酸素を取り込む”スピード”に特化した吸い方なので量は吸えません。
腹式呼吸は寝てる時やリラックスしてる時に自然に行っている吸い方です。
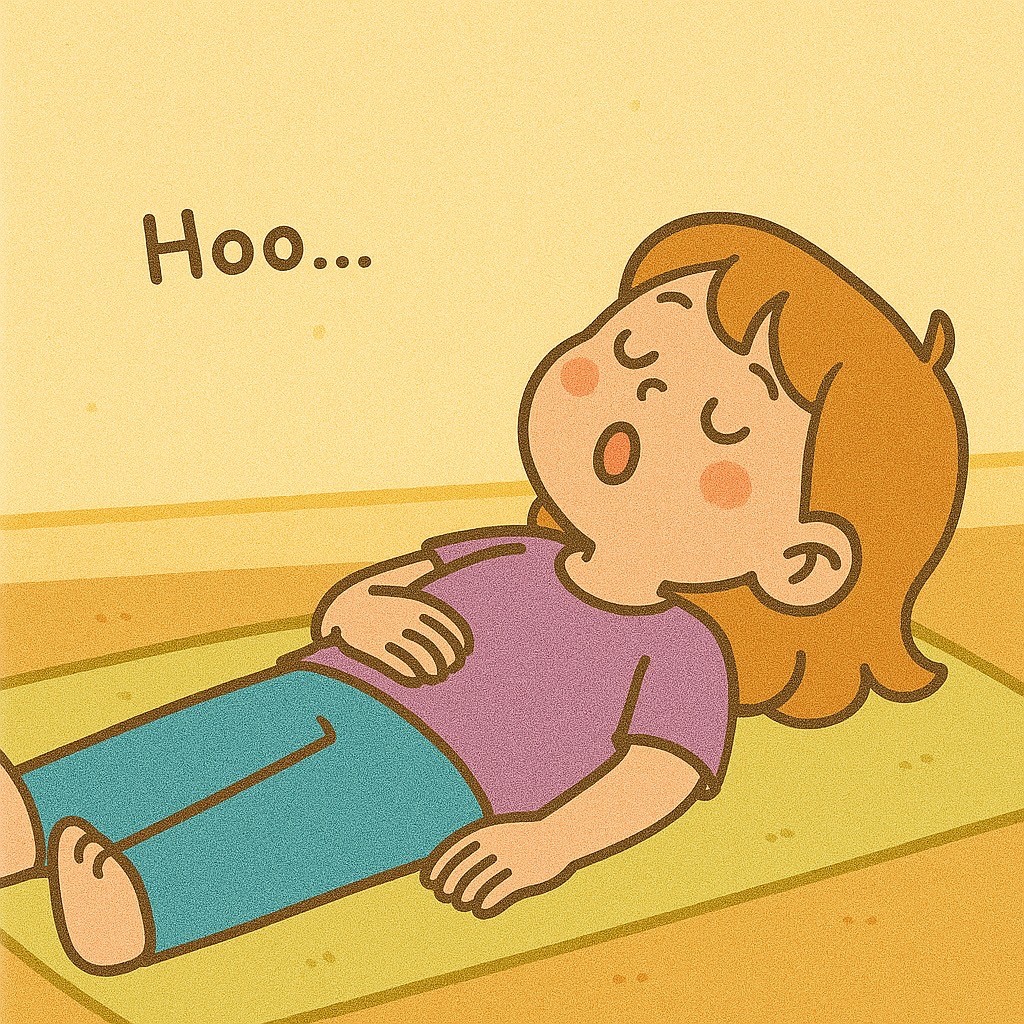
空気を吸うとお腹が膨らみ抜けると凹む、”風船と同じ動き方”をする呼吸です。
しっかり量が吸える方法です。
歌う時には想像以上の空気を使います。
そのため、よりたくさん空気が吸える腹式呼吸があちこちで推奨されているのです。
腹式呼吸の吸い方、吐き方のコツと練習方法
”吸い方”
鼻と口、両方一気に使って吸います。吸うとお腹が膨らみます。
その感覚を理解するために、使える方法があるのでご紹介いたします。
- いつも通り軽く息を吸う
- 酸欠になる手前まで「ふー」と息を吐き切る
- 止める
- 口を開けて息を吸う そうすると鼻と口両方で吸う感覚がわかると思います。その方法で吸った空気でお腹が膨らんでいればOKです。
”吐き方”
これも風船と一緒で、吐くとお腹がへこみます。「s〜」と吐いて見てください。
注意ポイントは「息が常に均一かどうか」「ある程度スピード感を保って吐けてるかどうか」です。
途中で増えたり減ったりしないようにしてください。
どちらも瞬間的に吸って吐けるように、手拍子に合わせてやってみてください。
「吸う 吐く吐く吐く吐く 吸う 吐く吐く吐く吐く」の要領で「ハッ スッスッスッスッ ハッ スッスッスッスッ…」と続けてみてください。
共鳴とは?
簡単に言うと音が響くかどうかです。トンネルを想像していただくと、わかりやすいかと思います。
ある程度囲まれた空間で音を出すと響いて大きく聞こえますよね?それを体の中で起こします。
トンネルとして利用できる空間は主に4つです。
- 喉、口腔、鼻腔(前・後)
喉周辺は声帯があるので、ずっと喉の響きで歌い続けるとしんどくなりやすいです。
おすすめは鼻の前の方を響かせる音を利用すること。
そうすると声帯から距離があるので、疲れにくくなります。この音はハミングで出せます。
ハミングとは口を閉じて舌を上顎に軽くくっつけながら「んー」と鳴らした音です。その時鼻が震えている感覚があれば、バッチリです。
響かせるためには
次はその声の波を増幅させるために、口腔内の空間を大きくとります。
まずは内側を開けるために、あくびをしてみてください。
そうすると上顎と喉の間の軟口蓋と呼ばれる部分が引き上がり、舌が引き下がる感覚があるかと思います。
それが内側から見た時に一番大きい状態です。
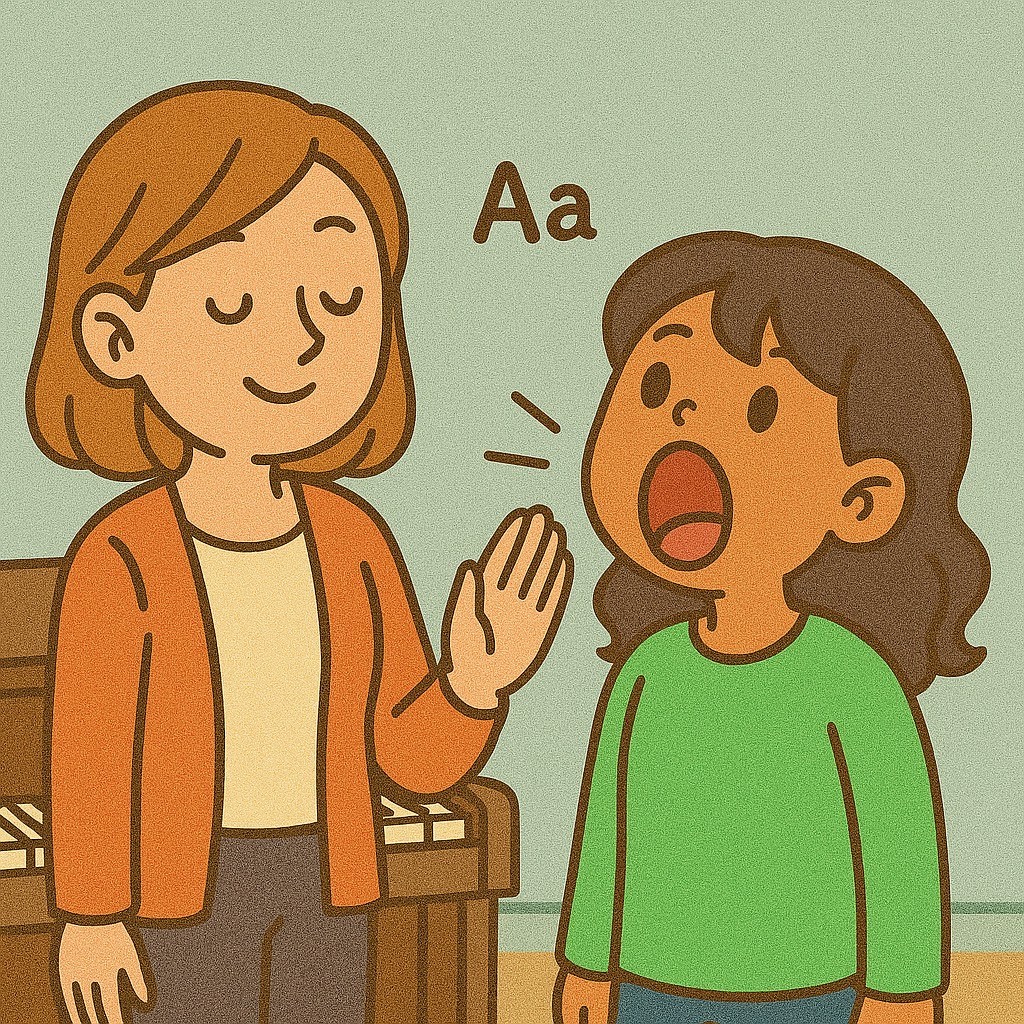
次は外側から大きくしてみましょう。
下顎の骨を重力に任せて、真下に落としてください。
そうするとアホヅラのようになりますが、それで正解です。
では、あくびの口とアホヅラの顎を同時に行ってみてください。
それが最大で口が大きい状態です。
ではハミング→あくびの口→アホヅラの顎 の順番でひとつづつ足していってください。
その時ハミングの位置や響きが後ろに下がってしまわないように気をつけながら行ってください。
声帯閉鎖とは?
声帯はそもそも、2枚の長方形の布が並んだような形をしています。長い辺同士が一箇所重なった状態です。
その重なった辺の端にある向かい合った角同士がくっついていると思ってください。
その長い辺が自分に対して縦に来るように想像してください。そうすると布を左右に引っ張った時、重なった辺のところが開いたり閉まったりしますね。
”その開閉する部分を閉めたまま、縦に伸ばしたり縮めたりしていきます。”
これが声帯閉鎖して発声した時の声帯の状態です。
いずれもリラックス状態で伸縮させます。

声帯閉鎖の練習方法
なぜ声帯閉鎖が必要かというと、小さな力で通る声を作れるからです。
これを手軽に練習できるのがエッジボイス(詳しくはこちら)です。
別名呪怨ボイスとも呼ばれますが、「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛」という声です。
この「あ゛」の間隔を広くしたり狭くしたりすることで、声帯閉鎖したまま声帯を伸縮する練習ができます。
ここまでが発声の基礎練習です。
ここからはもっと音楽的になっていきます。
音程の安定を目指す
音程は歌を歌うために、避けて通れない課題ですよね。
では安定して歌うためにどんな練習があるのか、みていきましょう。
”音程を正確にするための練習方法”
- まずは自分で歌って録音する
- 聞き返し、原曲と聴き比べてどこがずれているのか確認する。(耳に自信がなければ、鍵盤やチューナーで確認する)
- 1、2を繰り返した後、一文字単位でまっすぐ歌えるように練習する。*この時よくあるブレはアタックが強すぎ、しゃくり、意図していないビブラートです。あくまでもAIのようにまっすぐ歌ってください
これを繰り返し練習します。まっすぐ歌っても歌として成立するようになれば完璧です。
リズム感を養う練習方法
私個人としては音程よりもリズムのほうが大切だと思っています。
曲全体の雰囲気はリズムがより多くになっていると思うからです。
”リズムトレーニング”
楽器を聴く
まずはしっかり楽器に耳を傾けてください。
ドラムだけを聴く、ベースだけを聴く、ギターだけを聴く…といった感じで何度も何度も聞いてください。
その時に各楽器がどういうリズムで進んでいるのかをよく聞いてください。
”裏拍を感じながら歌う”
- 手を叩きながら歌ってみましょう。(多くの方は表で叩きながら歌うことになると思います)
- では倍のスピードで叩きながら歌いましょう。
- 手拍子が「・・・・」並んでいた場合「1212」と番号を振ります。
- 2の番号のところだけ叩きながら歌ってみてください。
2のところだけ叩きながら歌い切れたら成功です。
”グルーブの感じ方”
「リズム」の先にある「ノリ」のさらに先に「グルーブ」があります。
リズムが取れるようになったら、そのリズムに強弱や動きを感じてください。
その感じた動きを手や声を使わずに隣の人に伝えてみてください。
伝わってやっと「グルーブ」です。

表現力を高める
一番難しい工程ですが、もちろんこれも練習できます。
- まずは歌詞の意味や背景を理解しましょう。
- フレーズや単語単位で喜怒哀楽を配分します。(サビ前は嬉しい気持ちにするなど)
- 各感情の時にどんな喋り方になるか、研究してください。(嬉しい時→笑顔になる→同じ顔で歌うなど)
そうすると自然な抑揚がつきます。
あとは好きなの歌手の表現を参考にし、自分なりのスタイルを作っていきます。
それ以外にもテクニック(ビブラートやしゃくり、こぶしなど)はありますが、
上記の内容を習得すれば、ある程度自然にできるようになると思います。
継続的な練習とフィードバック
あとはひたすら続けてください。
お風呂タイムや通勤時間でもできるものはたくさんあるし何かひとつでもいいので、やり続けてください。筋トレと一緒です。
それでも難しいことやわからないことは、ボイストレーナーや仲間から意見をもらうといいと思います。
時々自分の歌を録音・分析し、修正すると改善ポイントがわかりやすくなり、成長スピードもグッと上がると思います。
よくある質問 Q&A
Q1. 腹式呼吸ができているかどうか、どうやって確認できますか?
→お腹に手を当てて、息を吸ったときに膨らみ、吐いたときにへこむかを確認しましょう。また、息を吐くたびにミゾオチから5センチくらい下のところはお腹が跳ね、お臍から5センチくらい下のところは凹むか確認してください。
Q2. ハミングのときに鼻が震える感じがわかりません。間違ってますか?
→口を閉じた状態で「んー」と出したとき、鼻先や頬のあたりがビリビリする感覚があればOKです。感じにくい場合は少し鼻に空気を通すように意識してみましょう。
Q3. エッジボイスをやったら喉が痛くなったんですが、やり方が悪い?
→喉が痛くなるのは力みすぎか、息を無理に押し出している可能性があります。一度中止して、リラックスした状態で出せるかを確認してください。無理は禁物です!
Q4. 音程のズレって、自分では気づきにくいんですが…
→録音した音声を、原曲と一緒に再生してみるとわかりやすいです。チューナーアプリを使うのもおすすめです。
Q5. リズムの裏拍がうまくとれません。どうすれば?
→手拍子を倍速で叩く練習や、メトロノームを使って裏にだけ合わせる練習を繰り返すと、徐々に慣れてきます。慣れるまではクラップだけの練習でもOK!
Q6. 感情表現がうまくできません。やっぱりセンスの問題?
→センスではなく「観察」と「模倣」が大切です。役者の演技を参考にする、好きな歌手の表情・声色・抑揚を真似るところから始めてみてください。
まとめ
歌の練習といってもこんなにやるべきことがあります。もはやスポーツと同じ感覚で練習していただいたほうがいいかもしれません。あとは継続するだけ!根気よく練習していきましょう
無料体験レッスンはこちら!

